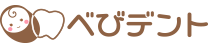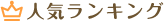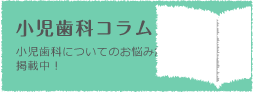子ども自身は、口内炎が原因で不快な症状を感じているとは気づけません。まわりの大人が子どもの異変を早めに察知して、歯医者さんの治療やホームケアを受けさせてあげることが大切です。子どもの口内炎について、この記事で正しい知識を身につけてくださいね。
この記事の目次
1.子どもの口内炎は気づきにくい

口内炎に苦しんでいる子どもの様子をすぐに感じとれるようになるためには、口内炎の症状を知っておかなければなりません。
子どもの口内炎に気づくポイント
小さな子どもほど、口内炎ができたことをうまく表現できません。とはいえ、口の中には痛みがあり、とてもつらい状態です。「機嫌が悪い」「泣いている」「食欲がない」などいつもと違う様子がみられたら、なにかしら原因があると考えてください。これらに加えて、食べ物をお口に入れたがらないときにはお口の中をチェックしましょう。
口内炎とは、お口の粘膜に起こる炎症のこと
お口の中やお口のまわりの粘膜に起こる炎症をまとめて口内炎と呼んでいます。食事だけでなく、呼吸や会話などでお口を開ける機会は多くあります。そのため、口内には細菌やウイルス、ほこりといった異物が入り込みやすくなっています。そこから内臓などに侵入していかないように、粘膜でガードしているのですが、その粘膜が細菌などによって炎症を起こしてしまうことがあるのです。
口内炎になるとあらわれる症状
口の中の粘膜が炎症を起こすと、次のような症状がみられます。
・赤く腫れる
・硬くなる
・水ぶくれができる
・傷ついてただれる
・血が出る
このように、粘膜がダメージを受けると痛みをともなうので、食べ物を口にすることが苦痛になってきます。口内炎のできる場所によっては、うまく飲み込めなくなる場合もあります。
2.どうして口内炎ができるの?
口内炎ができる原因は数多くありますが、子どもと大人では違いがあることを知っておきましょう。
口内炎にはいろいろな種類がある
細菌やウイルスの増殖のほか、疲労や免疫力の低下、物理的な刺激など、口内炎の原因はさまざまです。なかでも子どもに多いのは、ウイルスが原因の口内炎です。
以下で、主な口内炎の種類を紹介します。
ウイルス性口内炎
ウイルスが原因で起こる口内炎は子どもによくみられます。代表的なのが、ヘルパンギーナや手足口病です。単純ヘルペスウイルスに感染して発症するヘルペス性口内炎(口唇ヘルペス)もこのひとつです。
お口の粘膜に小さな水ぶくれがたくさんできて、やぶれてただれてしまうこともあります。発熱や強い痛みをともなうケースが多いのも特徴です。
カンジダ性口内炎
カンジダ性口内炎は、お口の中に存在しているカビの一種が原因で起こります。このカビがお口の中にいても、健康なときには特に問題はありません。ところが、子どものお口の中が不潔になったり体調を崩したり、抗生物質やステロイドなどの治療を受けたりすると、カンジダが増えやすくなるので注意が必要です。
コケのような白くて小さな斑点(はんてん)ができて、しみるような痛みが生じるでしょう。のどの奥や食道に症状があらわれる場合もあります。
アフタ性口内炎
アフタ性口内炎が起こる原因ははっきりわかっていませんが、ストレスや疲労による免疫力の低下、ビタミンB2をはじめとした栄養の不足、睡眠不足などが関係していると考えられています。10歳以下の女の子に多くみられるのも特徴といえるでしょう。
赤くふちどられた白いただれが、ほほや唇の内側、舌、歯ぐきなどにできてきます。
アレルギー性口内炎
特定の食べ物や薬物、金属によるアレルギー反応によって、炎症が起きてできる口内炎もあります。虫歯の治療で使われる金属にも注意しましょう。
アレルギー性口内炎の場合、アレルゲンが触れた範囲の粘膜に炎症が起きてただれます。
カタル性口内炎
口の中を噛んでしまったときや、矯正器具が粘膜にあたって細菌が繁殖した場合、もしくは熱いものや薬などの刺激によって起こる口内炎です。
お口の粘膜がめくれたようなびらん(糜爛)ができて、周囲は赤く腫れたようになるでしょう。唾液が増えてお口がくさくなったり、お口の中が熱く感じたりといった症状があらわれることもあります。食べ物の味がわかりにくくなるケースも少なくありません。
3.子どもに口内炎ができたら疑いたい病気
大人と違って、子どもの口内炎はほとんどがウイルス性です。特に、以下であげる病気が原因であることが多いので気をつけましょう。
ヘルパンギーナ
夏に流行しやすいウイルス感染症で、感染してから症状があらわれるまでの潜伏期間は2日~7日ほどです。急に38度以上の高熱が出て、1日~4日くらい続きます。
上顎やのどの上あたりに、小さな水ぶくれが数多くでき、それがやぶれてただれることもあります。ほとんどの場合、4日~6日で治るでしょう。
手足口病
同じく夏によくみられるウイルス性感染症で、潜伏期間は3日~4日ほどです。それほど高い熱は出ませんが、手のひらや足の裏、ひじ、ひざ、お口の中の粘膜、舌に水ぶくれがポツポツと数個できるのが特徴です。腹痛や下痢をともなうこともあるでしょう。たいていは7日~10日で治ります。
4.歯医者をはじめとした医療機関での治療
子どもに口内炎ができているとわかったときに悩んでしまうのが、病院へ連れて行くかどうかではないでしょうか。口内炎の状態を把握して、必要に応じて適切な治療を受けさせてあげましょう。
病院へ連れて行く目安は?
症状がお口全体に広がって、発熱や全身倦怠感といった症状が10日以上続くなどウイルス感染が疑われる症状がみられるときには、医療機関を受診して適切な治療を受けたほうがよいでしょう。
アフタ性口内炎の場合には1週間~10日ほどで自然に治るので、症状がひどくなければ病院へ連れて行く必要はありませんが、口内炎の種類は本当にさまざまあるため自己判断は危険です。治りが悪い口内炎に関しては、きちんと歯医者さんに診てもらうことをおすすめします。
口内炎の治療は何科に行けばいい?
口内炎は耳鼻咽喉科が専門といわれています。ほかにも歯医者さんや口腔外科、内科、皮膚科、小児科でも診療は可能です。
ただし、口内炎の診療ができるかは病院によって異なるので、事前の確認をおすすめします。
受診時に聞かれること
口内炎の診療では主に次のことを聞かれるはずです。事前に答えを準備していくと、診療がスムーズに進むでしょう。
・口内炎ができた時期
・口内炎が繰り返しできているか
・発熱はどれくらいか
・どれくらいの痛みがあるか
・飲食など日常生活に問題はないか
・口内炎以外の症状
・口の中を噛むことが多いか
診察のときには、ほかの病気が関連しているのかを確認しながら、治療の必要があるのかを判断していきます。
原因に合わせた治療が行われる
一般的に口内炎の治療では、軟膏(なんこう)などの塗り薬や貼り薬などを使って炎症を抑えますが、口内炎の種類によって必要となる治療は異なります。
●ウイルス性口内炎の場合
二次感染を防ぐために抗生剤を投与します。ヘルパンギーナや手足口病は特効薬がないので、解熱剤などを用いて自然に治るのを待つしかありません。
●カンジダ性口内炎
イソジンガーグルなどのうがい薬や抗真菌剤を投与します。
●アフタ性口内炎
ステロイド剤を投与して、うがい薬や洗口剤でお口の中をきれいに保ちます。
●アレルギー性口内炎
アレルギー症状に適した治療が必要となります。
●カタル性口内炎
矯正装置やお口の中の詰め物、歯の鋭端が擦れていたりする場合は、それを少し削ったりして原因の除去が必要で、時には一時的にステロイド剤を投与する場合もあります。
5.子どもに口内炎ができたときのホームケア

病院へ行くまでもない口内炎の場合や、病院で診療してもらったあとなどは、自宅で適切なケアをしてあげましょう。
軽い口内炎は家で様子をみてもいい
口内炎以外に目立った症状がなく、口内炎そのものの症状も軽い場合には、生活習慣を改善しながら様子をみても大丈夫です。
痛みなどがつらい場合には、口内炎に有効な内服薬や塗り薬、貼り薬、うがい薬などのOTC薬品を活用してもよいでしょう。OTC薬品とは医師の処方がなくても購入できる医薬品で、ドラッグストアなどに置いてあります。
口内炎のときには食事内容に気をつけて
スープやおかゆ、うどん、豆腐、茶わん蒸しなど、あまり噛まなくても飲み込めるものや、プリンやゼリー、アイスクリームなど口当たりのよいものを食べさせてあげましょう。ただし、甘いものは虫歯を誘発しやすいので、歯みがきなどのケアは怠らないようにしましょう。
また、熱いものや冷たすぎるものは患部に刺激を与えてしまうので、温度を調節してください。すっぱいものや固いものは口内炎が治るまでは控えましょう。
口内炎があると、飲み物も嫌がる傾向があります。必要な水分量をしっかりととらせてあげることが大切です。食事では、皮膚や粘膜を健康に保つのに必要なビタミンB2やビタミンB6、ビタミンCの摂取を意識したメニューを考えてあげましょう。
口内炎を早く治すために注意すべき生活習慣
免疫力を高めるために、睡眠を十分にとらせて規則正しい生活を心がけてください。また、うがい薬などを使ってお口の中を清潔に保つことも大切です。歯みがきをするときには、粘膜を傷つけないように気をつけてあげましょう。
6.まとめ
子どもの口内炎は、ヘルパンギーナや手足口病などウィルスが原因の可能性もあるので、ほかの症状があらわれていないかのチェックが肝心です。なにが原因で口内炎ができているのかによって、治療法が異なることも覚えておきましょう。
痛みなどを的確に表現できないお子さんの様子に早く気づき、口内炎のつらい症状からできるだけ守ってあげてください。無理して自分でなんとかしようとせずに、少しでも不安があったら歯医者さんに相談することも忘れないようにしましょう。